住宅改修・福祉用具購入について
1 住宅改修について
介護保険の住宅改修について
要支援及び要介護認定を受けた人が住み慣れた自宅で安心して自立した生活を送るために必要な住宅改修費の一部を介護サービスとして支給される制度です。
対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用のうち9割(一定以上の所得がある65歳以上の人は8割または7割)を支給します。
住宅改修費の支給対象となる改修費用の上限は、お一人につき20万円ですので、支給限度額は18万円(8割の場合は16万円、7割の場合は14万円)となります。
住宅改修費の給付を受けるには、改修を行う前に長寿介護課に事前申請を行い、承認を得る必要があります。承認を受ける前に行った改修は給付対象となりませんのでご注意ください。改修後に住宅改修費支給申請を行い、改修前に承認を受けた内容どおりの施工が確認された後に給付が行われます。
支払方法について
介護保険制度では、福祉用具を購入したときや住宅改修を行ったときは、いったん全額を事業者に支払い、その領収証を添えて申請すれば、9割~7割が返ってくる方法が原則となっています。これを「1.償還払い」といいます。
しかし、この方法では申請してから9割~7割が返ってくるまでに、約2か月の時間がかかってしまうため、利用者の負担となる可能性があります。
そこで、本市では利用者の経済的負担の軽減を図るため、「2.受領委任払い」を行っています。
「1.償還払い方式」を選択した場合、利用者が施工事業者に費用の全額を支払い、その後、9~7割が介護保険から利用者に支払われます。
「2.受領委任払い方式」を選択した場合、利用者が施工事業者に費用の1~3割の金額を支払い、その後、9~7割が介護保険から施行事業者へ支払われます。
受領委任の対象者
受領委任の対象者は、次のにいずれかに該当する者で、住宅改修費等に相当する費用の支払が特に困難と市長が認める者となります。
(1) 生活保護受給者
(2) 市県民税世帯非課税者
(3) その他特に市長が必要と認めた者
申請手続きについて
(1)申請様式について
介護保険を利用して住宅改修を行う場合は、以下の全ての要件を満たす必要があります。工事着工後の申請、事前承認前に着工した場合の工事は、保険給付対象外となりますので十分ご注意ください。
(1)被保険者証に記載のある住所の家屋に対する住宅改修であること。
(2)厚生労働大臣が定める住宅改修の種類の改修であること。
(3)被保険者本人の心身の状態や、家屋の状況等から総合的に判断し、自立した日常生活を送るのに必要な改修であると認められること。
(4)在宅で生活されていること。
(5)要介護認定を受け、有効期間内であること。
| 【事前申請】事前に提出いただく書類一式 | |
|---|---|
| 住宅改修申請書 | 介護保険住宅改修費支給申請書(Excelファイル:17.2KB) |
| 住宅改修が必要な理由書 | 住宅改修が必要な理由書(Excelファイル:39.5KB) |
| 工事費見積書 |
任意様式 |
| 改修箇所の家の見取り図 | 任意様式 |
| 着工前の写真貼付 | 任意様式 |
| 状況に応じて提出が必要なもの | ||
|---|---|---|
| 受領委任払いに係る申請書(様式第2号)・委任状(様式第3号) | 受領委任払いに係る申請書(様式第2号)・委任状(様式第3号)(Wordファイル:18.5KB) | |
| 受領委任払いに係る同意書(様式第1号) | 受領委任に係る同意書(様式第1号)(Wordファイル:11KB) | |
| 住宅改修の承諾書(申請者と所有者が異なる場合) | 住宅改修の承諾書(Wordファイル:10.5KB) | |
| 住宅改修の承諾書(住宅所有者が死亡している場合) | 住宅改修の承諾書(代表相続人)(Wordファイル:10.5KB) | |
| 給付関係申出書(振込先が申請者と異なる場合) | 給付関係申出書(Wordファイル:8.8KB) | |
| 生活保護受給者 ※受領委任払いとなります。長寿介護課へ提出してください。 |
委任状 |
委任状(Wordファイル:11KB) |
| 請求書 | 任意書式(利用者負担1割分の請求書) | |
(2)算定上の留意事項
- 介護認定申請中または入院・入所中の方について
介護認定中または入院中や施設入所中の方の、事前申請による事前承認後の工事着工は可能ですが、支給申請は、認定結果が出てから、または退院・退所した後になります(一時帰宅中の支給申請は認められません)。そのため、認定結果が「非該当」の場合は、住宅改修費の支給を受けることができなくなります。また、退院・退所の中止等により、申請中の住宅に居住できなくなった場合には、住宅改修費用の全額(退院後に再入院し、退院が中止になった場合には、再入院以降の工事金額)を自己負担していただくことになります。 - ひとつの住宅に複数の被保険者がいる場合の改修について
住宅改修費の支給限度額の管理は、被保険者ごとに行われるため、被保険者ごとに支給申請を行うことができます。ただし、複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合、各被保険者ごとに対象となる工事を設定し、内容や場所等が重複しないよう申請してください。 - 支給対象の工事内容について
支給の対象となる工事内容であるかどうかは、保険者である小林市が決定します。同じ工事内容でも保険者ごとに判断が異なる場合がありますので、支給の対象となる工事かどうか分からない場合は、直接市長寿介護課へお問い合わせください。 - 住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われた場合
住宅改修費の支給対象となる住宅改修に併せて支給対象外の工事も行われた場合は、対象部分の抽出、按分等適切な方法により、住宅改修費の支給対象となる費用を算出してください。 - 被保険者等自らが住宅改修を行った場合
被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とします。この場合、「住宅改修に要した費用に係る領収証」は、材料を販売した者が発行したものとし、これに添付する工事費内訳書として、使用した材料の内訳を記載した書類を本人又は家族等が作成することとなります。なお、この場合であっても、必要となる書類に変更はないのでご留意ください。
よくある質問Q&A
Q1.既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。
A1.既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由であれば支給対象となります。しかし、引き戸が古くなったため新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはなりません。
Q2.同居する夫婦が共に要介護者の場合の2人が使用する浴室の住宅改修はどのようにすればよいか。
A2.各々の要介護者に対して有益な住宅改修を特定する必要があります。夫婦で改修が必要な場合でも、同一の住宅改修である場合には、重複して支給することはできません。
Q3.和式便器を洋式便器に改修する際、仮設トイレを設置した場合、仮設トイレの設置費用は支給対象となるか。
A3.仮設トイレの設置は、トイレの改修工事に直接的に関与するものではないため、支給対象対象とはなりません。
Q4.改修の際に不要となった便器・扉等の撤去費用および処分費用は給付対象となるか。
A4.工事に係る付帯工事となるため、給付対象となる。
Q5.着工時点においては存命だった被保険者が、住宅改修完了前に死亡した場合、保険給付を受けることは可能か。
A5.死亡時に完成している部分が介護保険の給付対象として申請できます。(被保険者の死亡時までの工事完了部分の経費が対象となります。)
2 福祉用具購入について
介護保険の福祉用具購入について
介護保険制度における要支援または要介護の認定を受けた方が、在宅で生活するために、身体状況に合う下記の福祉用具を「特定(介護予防)福祉用具販売事業所」から購入した場合、同一年度内(4月~翌年3月)につき購入経費(上限額10万円)から自己負担分を除いた額が支給されます。
介護保険における福祉用具は、利用者がその居宅において引き続き自立した日常生活を営むことができるよう必要と認められるものを保険給付の対象としています。
また、対象種目は、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うものや使用によって元の形態・品質が変化してしまうものを保険給付の対象としています。
支給限度基準額は同一年度で 10 万円
福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4 月 1 日からの 12 か月間)で 10 万円です。したがって、居宅介護福祉用具購入費と介護予防福祉用具購入費の総額は、10 万円の 9 割(8 割、7 割)相当額を超えることはできません。また、同一年度内に一度、福祉用具購入費が支給されると、以後の期間に同一種目の特定(介護予防)福祉用具について福祉用具購入費は支給されません。したがって、初回に 7 万円分の福祉用具購入費を受けた場合、その年度は残り 3 万円までを他種目の特定(介護予防)福祉用具に充てることになります。
支給要件について
(1)担当のケアマネジャー等が必要性を居宅サービス計画に位置付けていること
(2)購入する福祉用具が支給対象となる種類(特定福祉用具)であること
※公益財団法人テクノエイド協会の『福祉用具情報システム(TAIS)』で確認できます。
(3)特定(介護予防)福祉用具販売事業所として都道府県や政令指定都市等による指定を受けた介護保険サービス事業所(以下、販売事業所という。)から購入していること
※小林市の場合は特に事業所の指定はありません。
同一品目の再購入について
原則として、同一品目の再購入にかかる給付費の支給はありませんが、次の場合については認められることもありますので、事前にケアマネジャーを通じて市にご相談ください。
(1)特定(介護予防)福祉用具が破損した場合
通常の使用方法に則り、使用していた福祉用具が経年劣化で破損した場合等が考えられます。このとき、故意による破損は対象とはなりませんのでご注意ください。 経年劣化年数は福祉用具の種目によります。また、部品交換で修復が可能な場合は、部品も対象となります。
(2)被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
前回の購入時の要介護度よりも介護度が高くなることに加え、購入当初のケアプランから大きく内容を変更する必要があるほど、身体状況が著しく悪化した場合が考えられます。この場合、既に購入した福祉用具の使用が困難であり、機能面を著しく見直す必要性について、介護状況や身体状況の変化にかかる経緯や再購入の合理性を考慮した説明が必要となります。
(3) 特別の事情がある場合
災害を原因とする床上浸水等による流出や家屋倒壊による破損等が考えられます。
高額・高機能製品の購入について
高額で高機能を持つ福祉用具とは、一般的に、通常の福祉用具に対して一定以上の機能が付加されているもので、材質・仕様等が高品質なために高額となっているものを指します。
高額・高機能製品の購入にあたっては、ケアマネジャーのケアマネジメントをとおしてその必要性を明らかにして、高額・高機能 福祉用具購入理由書(Wordファイル:10.7KB)をご提出ください。
以下の判断基準等に留意しながら、現状の課題、心身の状況、介護負担の状況、福祉用具の導入によって得られる暮らし等について記載してください。ただし、居宅サービス計画書(介護予防サービス支援計画書)中に、その内容が含まれている場合は、理由書は計画書を添付することで代用できるものとします。
| 判断基準 |
主治医等からの意見により必要であると判断されるもの(疾病・身体機能低下) |
| 在宅介護の負担軽減(肉体的・心理的負担軽減) | |
| 本人の自立生活支援に資するもの |
申請手続きについて
| 提出いただく書類一式 | |
|---|---|
|
福祉用具購入費支給申請書 |
|
|
福祉用具の購入に係る領収書(全額) |
販売事業所が発行する領収書 |
| 用具のパンフレット等 |
機能・構造及び製造業者等の基本情報が確認できるもの |
|
状況に応じて提出が必要なもの |
||
|---|---|---|
|
受領委任払いに係る申請書(様式第2号)・委任状(様式第3号) |
||
|
受領委任払いに係る同意書(様式第1号) |
受領委任に係る同意書(様式第1号)(Wordファイル:11KB) | |
|
給付関係申出書(振込先が申請者と異なる場合) |
||
| 高額・高機能 福祉用具購入理由書 | 高額・高機能 福祉用具購入理由書(Wordファイル:10.7KB) 高額・高機能 福祉用具購入理由書(PDFファイル:71.9KB) |
|
|
生活保護受給者 |
委任状 |
委任状(Wordファイル:11KB) |
|
請求書 |
任意書式(利用者負担1割分の請求書) |
|
よくある質問Q&A
Q1.介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入は、福祉用具購入費の対象となるか。シャワーチェアのパッドの劣化が激しいため、パッド部分のみを交換したいが、対象となるか。
A1.福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市が部品を交換することが必要と認める場合には、介護保険の適用対象となります。
Q2.技術の進歩とともに、特定福祉用具そのものの機能もいろいろと付加されてきており、暖房・脱臭機能付きのポータブルトイレをご家族が購入希望である。購入の判断基準等があれば示してほしい。
A2.高額で高機能をもつ福祉用具の購入については、ケアマネジメントをとおしてその福祉用具の必要性を明らかにする必要がありますので、福祉用具購入費申請書とともに「高額・高機能 福祉用具購入理由書」の提出をお願いします。給付対象となるかどうか不明な場合は事前に市にご相談ください。ただし、居宅サービス計画書(介護予防サービス支援計画書)中に、当該内容が含まれている場合は、理由書は計画書を添付することで代用できるものとします。
(判断基準)
・主治医等からの意見により必要であると判断されるもの(疾病・身体機能低下)
・在宅介護の負担軽減(肉体的・心理的負担軽減)
・本人の自立生活支援に資するもの
※ケアマネージャーの判断に基づき提出をお願いしています。市から理由書の提出を求めることもありますので、ご留意ください。
Q3.選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画または介護予防サービス計画に位置付ける場合、主治医意見書や診療情報提供書に福祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師に照会する必要があるか。
A3.追加で医師へ照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会は要しない。
Q4.ウォシュレット付き補高便座は福祉用具の購入対象となるか。
A4.テクノエイド協会で福祉用具購入の対象となっている商品を原則支給対象とします。なお、補高便座については、あくまでも「補高を目的」としている場合に支給対象となるので、洗浄機能のみを目的とした場合は支給対象となりません。
※ウォシュレットのほか、暖房、消臭機能の場合も同様の取扱いとします。
Q5.年度途中で1割から2割に負担割合の変更があった方に対する福祉用具購入の支給について、いつ時点の負担割合に基づいて支給するのか。
A5.領収書記載日時点における負担割合を適用するため、領収日が基準日となります。
Q6.貸与と販売の提案に係る利用者の選択に資する情報提供について、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必要な情報とはどういったものが考えられるか。
A6.選択性の対象福祉用具は、利用者が購入の判断を行いやすい比較的廉価なもので、平均貸与月数が長い若しくは同等、かつ、分岐月数より長く利用している者の割合が相対的に高いものが対象となっています。
利用者の選択に当たって必要な情報としては、以下のとおりです。
- 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
- サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し
- 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
- 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること
- 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
- 国が示している福祉用具の平均的な利用月数(※) 等
※ 選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数
・固定用スロープ:13.2ヶ月
・歩行器:11.0ヶ月
・単点杖:14.6ヶ月
・多点杖:14.3ヶ月 (出典:介護保険総合データベース)
参照「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1225)問101(令和6年3月 15 日発出)
Q7.選択制の対象種目の販売後のメンテナンス等に係る費用は利用者が負担するのか。
A7.販売後のメンテナンス等にかかる費用の取扱いについては、利用者と事業所の個別契約に基づき、決定されるものと考えている。
参照「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1225)問104(令和6年3月15 日発出)
購入を選択した場合、メンテナンス費用、修理費用等が自費での契約になることから、購入によるメリット・デメリットを事前に説明し、判断することが求められます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
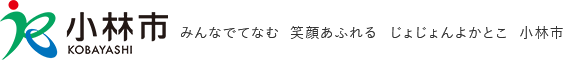
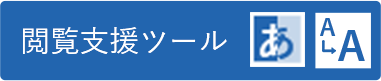



更新日:2025年03月04日