マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(マイナ保険証)
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申込みしたマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードを医療機関等の受付に設置しているカードリーダー(認証用端末)にかざすことで、医療保険の資格情報をオンラインで確認でき、医療を受けることができます。
(注)カードリーダー(認証用端末)が設置されていない医療機関などでは、これまでどおり健康保険証を窓口で見せてください。
(注)マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用登録は任意です。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の利用をお願いします
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は、令和6年12月2日から新規の発行ができなくなります。
令和6年12月1日までに発行している国民健康保険証をお持ちの方は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引き続き利用できます。
ただし、以下の方は有効期限が異なりますので、ご注意ください。
1.令和7年7月までに75歳の誕生日を迎える人(有効期限は誕生日の前日)
2.令和7年7月までに70歳の誕生日を迎える人(有効期限は誕生月の月末、お誕生日が1日の方は前月末)

マイナ保険証を利用するメリット
1.より良い医療を受けることができる
過去に処方された薬の情報や健康診断の結果をマイナポータルで確認できます。本人が同意すれば医療機関でも確認できるため、より多くの情報をもとに診療や薬の管理ができるようになります。
2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
医療機関などの窓口での支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月に支払う医療費の自己負担額の上限を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」という制度があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担となります。
そこで1か月に支払う医療費が最初から自己負担限度額までとなるように医療機関などの窓口で見せていただく「限度額適用認定証」があります。
ほけん課の窓口で事前に交付の申請が必要ですが、マイナ保険証を利用すると「限度額適用認定証」がなくても高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。
(注)保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額などは限度額の対象に含みません。
3.医療費控除が簡単になる
マイナポータルを通じた、医療費通知情報の自動入力で、簡単に確定申告の医療費控除の手続きができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm
4.健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越しをしてもマイナ保険証をずっと使うことができます。
(注)ただし、国民健康保険の加入脱退による異動があった場合は、ご自身で保険者へ手続きをする必要があります。
令和6年12月2日以降の対応について
令和6年12月2日以降、国民健康保険証紛失等による再発行を含め、新たに国民健康保険に加入した人や転居などをした人は、国民健康保険証の代わりとなるものを交付します。
【新規で国民健康保険に加入する人】
・マイナ保険証の利用登録がない人には健康保険証と同じように医療機関で使える「資格確認書」を交付します。「資格確認書」だけで受診できます。
・マイナ保険証の利用登録がある人には医療保険の資格情報をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を医療機関などのカードリーダーで読み込めない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に見せることで、保険診療を受けることが可能となります。
【国民健康保険証を紛失した人】
・申請により「資格確認書」を交付します。
【電子証明書の更新を忘れた人】
保険者が対象者を把握し「資格確認書」を交付予定です。
(注)電子証明書とは、マイナンバーカード交付時に設定した電子証明書用の暗証番号(数字4桁)のことです。
再度設定が必要なので、本庁市民課・須木住民生活課・野尻住民生活課窓口へお越しください。

マイナ保険証の利用登録方法
マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で事前の利用申込みが必要です。
1.セブン銀行ATMで登録
2.マイナポータルで登録
3.医療機関の窓口で登録
4.小林市役所市民課窓口で登録
DV・虐待などから被害支援措置を受けている人へ
DVなどの被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限などの支援措置を受けている人は、加害者やその関係者からマイナポータルを利用した住所などを含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は、毎年7月頃に「資格確認書」を送付しますので、病院を受診する時には「資格確認書」を窓口で見せてください。
国民健康保険税の滞納がある人へ
・国民健康保険税を納めずにいると、他の納税者との公平を保つことや税収を確保するために、財産(不動産、預金、給与など)を差押え、その後は公売などを行い、滞納税額へ充てることとなります。
また、災害、事業の休廃止や病気など、保険税を納付することができない特別な事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険税を納付しない場合には、特別療養費の支給対象(注)となります。
(注)特別療養費の支給対象になると、医療費を一旦全額負担(10割負担)し、医療費の支払い後、領収書を持参いただき、市の窓口で申請することで、一部負担金(自己負担額)を除いた療養費の払い戻しを受けることになります。
よくあるご質問
Q1 すべての医療機関や薬局でマイナ保険証を使えるようになりますか?
A1 マイナ保険証を利用できるのは、マイナンバーカードのカードリーダー(認証用端末)を導入している医療機関と薬局だけです。
カードリーダーが導入されていない医療機関などでの受診には、引き続き健康保険証を窓口で見せてください。
Q2 医療機関や薬局での受付はどのようになりますか?
A2 マイナ保険証を利用される人は、マイナンバーカードを受付窓口のカードリーダー(認証用端末)に置いたあと、顔認証または暗証番号の入力で、本人確認が行われます。
健康保険証や資格確認書を利用される人は、従来どおり受付窓口で健康保険証もしくは資格確認書を見せてください。
Q3 マイナンバーカードの健康保険証の登録は解除できますか?
A3 加入している保険者(お住まいの自治体の国民健康保険、全国健康保険協会、共済組合など)に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができます。利用登録解除の申請をしたあと、保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることができます。
具体的な解除手続きについては、ご自身が加入している保険者に対してお問い合わせください。
(注)ご自身が加入している保険者については、お持ちの保険証に記載されているのでご確認ください。
なお、小林市の国民健康保険に加入している人については令和6年12月2日以降受付予定ですので、窓口にお越しください。
Q4 加入している健康保険が変わったとき、再度マイナンバーカードの健康保険証利用登録は必要ですか?
A4 必要ありません。
ただし、健康保険の切り替え手続きをしてから新しい健康保険情報がオンライン資格確認システムに反映されるまでに時間がかかりますので、ご了承ください。
Q5 マイナ保険証の利用登録をしたか覚えていません。どうすれば確認できますか?
A5 ご自身のマイナポータルにログインして確認することができます。
ご自身のスマートフォンやカードリーダー付きのパソコンからマイナポータルにログインしてください。
Q6 マイナ保険証を利用できる医療機関や薬局は、どうすれば知ることができますか?
A6 厚生労働省のホームページで確認することができます。
また、利用できる医療機関や薬局においても、マイナ保険証を利用できることが分かるようにポスターなどが貼られています。
Q7 医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーカードを預けるのですか?
A7 医療機関や薬局の受付窓口では、マイナンバーカードを預かりません。
Q8 医療機関や薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか?
A8 医療機関や薬局では、マイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードの「電子証明書」を利用します。
また、マイナンバーカードには、ご自身の受診歴や診療情報などの個人情報は記録されません。
Q9 既にマイナ保険証の登録をしている場合、社会保険から国民健康保険へ切り替わっても手続きは必要ですか?
A9 社会保険から国民健康保険へ切り替えるなど、保険者が変わる場合は、ほけん課窓口で手続きが必要です。
(自動で切り替えすることはできません。)
Q10 小林市以外の自治体の国民健康保険に加入しており、転居のため小林市へ転入を予定していますが、すでにマイナ保険証の登録をしている場合、国民健康保険の手続きは必要ですか?
A10 同じ国民健康保険でも保険者が異なりますので、ほけん課窓口で手続きが必要です。
その他の質問については下記のホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ
「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html
外部リンク
マイナンバーカードについて詳しくはこちらをご覧ください。
総務省ホームページ
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
マイナ保険証について詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
手続き窓口
【問い合せ先】
小林市役所 ほけん課
国保グループ電話 0984-23-0116
【手続き窓口】
小林市役所 ほけん課
須木庁舎・野尻庁舎(住民生活課)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 ほけん課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
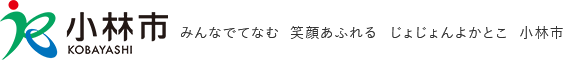
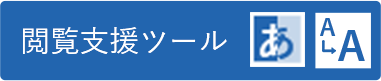



更新日:2024年11月05日