輪太鼓踊(わだいこおどり)
この踊りは、豊臣秀吉の朝鮮出兵から始まったと伝えられています。このとき、島津の軍勢は泗川の戦いで士気を鼓舞するため鐘や太鼓を打ち鳴らしつつ踊りながら敵陣に入り、奮戦しました。その勇壮な様子を舞踏化したものといわれています。その後、平時の軍事訓練として薩摩藩内で行われ、江戸時代の中頃には農民の間に広まって小林に伝わったとされています。昭和37年に東方地区、細野地区ともに県の無形民俗文化財に指定されています。

- 流し踊りを始めることの前奏曲で、次の踊りを強めるために
- 門掛り固め堅き城門を打破る時に使われた勇壮な踊り。
鐘太鼓の音も強く城門を打ち破る勢いあり - 庭入り城門から内庭に入ったことを表す
- 四つ這這い這い城の本拠に近づく様を表す
- 道鐘本拠本丸に向かって八方の登り道を進む様を表す
- 打切り
- 幕入り本陣近くの幕に突入する様を表す
- 城攻め本拠一の丸を攻むる様を表す
- 山道曲がりくねった山道を登り行く様を表す
- 打切り
- 幕入り本陣近くの幕を蹴飛ばす様を表す
- 城攻め本陣に向かって攻め立つる様を表す
- 打上げ
- 流し
- 打切り
- 馬攻め馬を以て一気に攻上る様を表す
- 打切り

以上、門掛り、四つ這、道鐘、城攻め、馬攻めを主体として、その他は踊りのつなぎとして使われて、踊りにあやを付けたものです。
種別
県指定無形民俗文化財
指定日
昭和37年5月15日
所在地
小林市東方地区、細野地区
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 社会教育課
〒886-0004
宮崎県小林市細野38番地1 小林中央公民館
電話番号:0984-22-7912
ファックス:0984-23-9700
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
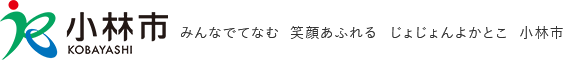
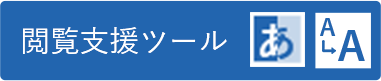



更新日:2022年02月18日